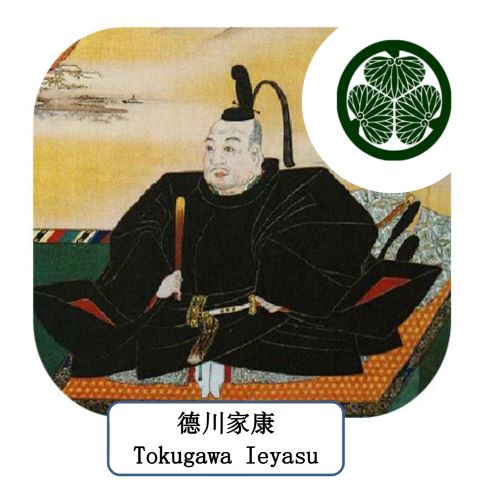名古屋城は徳川家康の命によって 1610 年築城を開始し、1612 年に天守が完成しました。
家康は、1603 年に征夷大将軍になり、江戸に幕府を開きました。
しかし、家康が政権を握った当時、大坂城には豊臣秀吉の遺児、秀頼がおり、豊臣恩顧の西国大名たちが反撃するのを恐れていました。
そこで大坂城を囲むように主要街道沿いに城を新築したり、改修したりしました。
その総仕上げとなったのが名古屋城の築城でした。
城主は家康の九男、徳川義直でした。1615 年、本丸御殿が完成しました。
その同じ年、家康は大阪夏の陣で秀頼を滅ぼしました。義直も出陣しました。
その後約 260 年間、義直の後継者(御三家の筆頭の尾張徳川家)がこの城に住んで尾張を治めていました。
1945 年、天守、本丸御殿などの建物が第二次世界大戦中の空襲で焼失しました。
その後 1959 年に鉄骨鉄筋コンクリート造で天守は再建されましたが、2018 年 5 月、建物の老朽化や建築基準法改正による耐震診断の結果、耐震性が低いと指摘され、見学者の安全を守るため閉館されました。
現在、天守は江戸時代の木造建築での復元が計画されています。
2018 年 6 月には、本丸御殿の復元が完成し、全体公開となりました。
江戸時代の名古屋城は、本丸、二之丸、西之丸、御深井丸(おふけまる)、三之丸までも含む区域で、現在の名古屋城(有料区域)の4倍を超える広さでした。
名城公園辺りにあった下御深井御庭も範囲に入れる場合もあります。
本丸は内堀で囲まれた区域で、天守と本丸御殿が建つ最も重要な場所でした。
二之丸には二之丸御殿が建ち、藩主が住み、家臣が通い、政務を行いました。
西之丸には米蔵が建ち並んでいました。
御深井丸は武器弾薬庫や塩蔵があり、人質屋敷もありました。
三之丸には、敵の侵入の備えとして重臣の武家屋敷が配置されていました。
約 260 年間続いた江戸時代が終わった明治時代の初め(現在から約 150 年前)、これらの武家屋敷は取り壊されました。
現在この辺りは地方官庁街になっています。
[A]那古野城那古野城は16世紀前半今川義元の弟氏豊の居城でしたが、中頃、織田信長の勢いが増す時代となり、信長は弘治元年に清洲城を奪い取り、それまで自分の本拠としていた那古野城を叔父織田信光に与えました。
ところが、信光が急死したので、その後、重臣の林通勝を入れたものの、やがて追放きれてしまい、那古野城は主を失いました。
信長は永禄六年に小牧山に城を造るまでは清洲城を居城にしていました。桶狭間の戦いは、清洲城から出陣しました。
信長が小牧山に移った後、清洲城は、織田信雄、福島正則、徳川家康の四男・松平忠吉の居城となり、そし家康の九男・義直が入りました。
関ヶ原の戦い後も豊臣方を牽制するために、家康にとって尾張は重要な土地でした。
当時、大坂は豊臣が城を構え、家康は秀頼と戦う時が来ると考えていました。
関ヶ原の戦いで勝利をおさめたとはいえ、豊臣方に心を寄せる大名も多く、油断は出来ませんでした。
江戸に直結する東海道の防衛のためにも、徳川の砦として、尾張の守りを早々に固める必要がありました。
その為に、清洲城に四男松平忠吉、九男義直を入れると同時に、続いて名古屋城築城の計画を選めました。
[B]清洲越関ヶ原の戦いで勝った家康も、西国からの新たな攻めに対して盤石の備えを考案しました。
その結果、町ごと引っ越すことになってしまいました。
家康は、義直を清須城の城主にするのを機会に、城の大修理を計画し、家臣たちにいろいろなプランを求めたのです。
そのなかの一人、山下氏勝は「修理するくらいなら、もっと立地のいい場所に新しい城を築いてはどうか」と提案しました。
その理由は、尾張南西の低地に位置する清須は、木曽川や五条川、北西には沼沢もあり、水攻めを受ければ大打撃を受ける。そうした理由から、那古野(名古屋)へ移転してはどうかというものでした。
那古野は、乾いた台地で熱田の海に近く、東西の交通も開け、大軍を動かすのに都合が良く、まさに城を築くのに恵まれた立地だ、というわけです。
当初、家康は小牧や古渡も候補地と考えていたため、提案をすぐに受け入れることがなかったものの、義直の母で家康の側室・お亀の方が、提案者・氏勝の妻の姉でもある関係で、名古屋に新城の築造を決断しました。
慶長十四年十一月、名古屋遷府を命令し、清須の町をまるまる名古屋へ引っ越すことに決定したのです。
計画を進める総合プロデューサーはもちろん家康であったのでしょう。
翌年、城の普請と合わせて町の移転も始まりました。
[C]縄張り城郭は軍事施設ですので、戦時の攻防を前提に設計されています。
城などの設計や実際に測量して区割りすることを「縄張」といいます。
まだ縄が主要な測量道具だったときにできた言葉です。広い意味で、築城計画全体を指し示すこともあったようです。
できあがった縄張を見て気づくのが三之丸の広さもさることながら、直線的なブロックで構成されていることです。
戦国時代まっただなかに造られた城は一気に攻め込めないように複雑な構成で本丸につながるルートも折れ曲がり、前方の視界をさえぎる複雑なものになっています。
これに比べると名古屋城はいたってシンブルな縄張です。
家康は築城にあたって、多くの大名たちに命じて工事を分担(天下普請)させました。
ということは、大名たちは名古屋城の縄張を知ることになります。
謀反を起こして攻めようと思えば、攻め込むルートや秘密までも知っていることになります。
ところが、名古屋城はどう攻めても絶対に破れない巧妙で、堅固な構造なのです。
虎口(城の囲いの入口)での堅い造り、四隅に巨大な櫓、多門櫓の規模も壮大で、敵になるかもしれない大名たちに知られても大丈夫というわけです。
それにもまして、家康の自信と狙いが反映された縄張が名古屋城の偉大さ、品格の高さに結びついているのです。
[D]石垣石垣工事を命ぜられたのは、もと豊臣家臣の外様大名二十家です。なかでも加藤清正は大活躍しました。
築城の順番として、まず曲輪の配置(縄張)を決めます。次に普請(石垣などの土木工事)に移り、根石置き工事から石積みへと石垣の築造にかかります。
名古屋城では、慶長十五年に入るや早々に始められた「縄張」が五月には完了しました。
約」ヵ月後の六月、本丸の根石置き工事が始まりました。ただ石を積むだけでなく、採石し、運搬、さらに寸法を調整したうえでの工事です。
現在のように機械化されていないなかで、清正は、なんと八月二十七日に持ち場であった天守台の工事を三ヵ月足らずで終えてしまったのです。
九月末には、諸大名も本丸、二之丸、西之丸、御深井丸の工事をほとんど完了し帰国しました。最終的には年末までかかった個所もありました。
現在も残る優美な石垣(天守台石垣は、宝暦大修理で北西角を中心に大部分は直されました)は、約四百年も前の夏に築かれたものです。
[E]作事石垣(普請)の次は、いよいよ天守の建築工事(作事)です。
家康は側近の中井大和守正清を大工棟梁に任命します。建築工事の技術的な設計・計画を担当する責任者です。
作事奉行は小堀遠江守政一(九人の作事奉行のうちの一人)です。
二人は、駿府域の作事も務めたベテランで良いコンビであったようです。
材木の大部分は、木曽の山から切り出した檜です。木曽の山から木曽川を利用して八百津あたりまで流し、そこで筏を組み河口へ。さらに海を渡って熱田へというルートが考えられています。
櫓は、品質の高い木曽檜です。しかもそれをぜいたくに活用して、丈夫さもさることながら、主に松や杉を使った他の城の天守閣と比べて豪華さも格別です。さすがに家康の名古屋城というわけです。
天守は、石垣工事の完成から二年後の慶長十七年十二月にほぼ完成しました。
[G]家康徳川家康には二つのめでたい出来事がありました。ひとつは関ヶ原の戦いに勝利したこと。もうひとつは、九男・黄直の誕生です。
時は慶長五年、家康五十八歳。家康は義直が老いてからの子ということもあり駿府城において、かわいがり育てました。
義直が家康のもとから離れて独立し、名古屋城へ入るのは元和二年のことです。
それまで甲斐や清須に封じられますが、義直自身は、生母、お亀の方とともに瞳府城にいました。
慶長十九年の大坂冬の陣で初陣を飾った義直は、四月に紀州和歌山の領主・浅野幸長の次女春姫と結婚。
その後、また駿府へ帰り、翌年(元和二年)四月の家康の死去にともない、同年七月に尾張へ入国しました。
幼年より城主となった義直ですが、自らが政治を行うようになったのは元和三年の十八歳になってからのことのようです。
さまざまな実績を残す義直の政治の考えは尊皇思想であり、後の藩風のベースになります。
[H]義直家康の九男・義直に始まる尾張徳川家は、紀伊・水戸の両家とともに徳川御三家として重きをなし、尾張家は兄の家柄として、その筆頭と目されました。
支配地域も尾張一国のほか、美濃・三河・信濃木曽、近江・摂津にまたがる広大なものです。
義直は、寛永三年に大名として最高の、従二位権大納言という高い官位に任ぜられます。
その義直は、藩の政治において実力を発揮します。
立藩まもない尾張藩政の基礎をかため、農業用のため池や新田の開発に尽力。さらに瀬戸の窯業の保護・奨励に力をそそぐなど、幅広い政策を推進し、数々の実績をあげました。
父家康の教えを守り文武両道に励んだ義直の秀でた力は顕著です。
まず、学間の世界では儒学を奨励し、寛永九年に「孔子堂」を建立。また歴史書「類累日本紀」著し、神道を説き由緒ある神社の祭神について考察を加えた 『神祇宝典』も著すなど、好学の気風を発揮します。
義直はまた、家康の形見分け「駿河御譲り本」に、自らが収集した請書を収蔵する文庫を城内に建てました。これは「御文庫」といわれ、今日の蓬左文庫のもとであり、図書館の起こりともされるものです。
[ I ]宝暦大修理半世紀余りが過ぎた寛文九年に、屋根や瓦、壁のしっくいなどの手入れが行われました。その後もほぼ十年ごとに修理がなされました。
1世紀以上もたつと、さすがに大がかりな修理が必要になってきました。
よくよく見ると、石垣が沈み、西北方向に天守閣が傾き、手入れ程度ではすまされない状態になりました。
宝暦二年、八代藩主・宗勝はいよいよ築後百四十年の名古屋城の大修理を断行しました。
大がかりなのは加藤清正が手がけた天守台の石垣の積み直しです。石垣の四隅に「井」型に材料を組み上げ。天守閣をテコで六十センチほど特ち上げます。その中央部下に、一層堅固な「井」型を組み、両サイドの石を取り除き、テコの原理を応用して天守閣を一方に傾斜させておき、下の石垣を組み直します。実に冒険的な工法の採用です。
この修理で、西北面の石垣の大部分が組み替えられました。
さらに、天守の一部の解体直し、三、四重目の土瓦を五重目と同じ銅瓦に、破風を銅板張りに、銅製の雨樋も施しました。
これにより城の天守は明治二十四年に発生した濃農尾大地震にも耐えることができたのかもしれません。
[J ]陸軍いよいよ日本の歴史は近代から現代へ。幕末から維新の動乱に起きたかずかずの事件を経て、明治元年、新政府の発足です。
政府は旧幕府や幕臣の領地を没収(版籍奉還)するなどして、近代国家への道を歩き始めます。政府の強化のためには、軍制を改めて、近代的な軍隊をつくることも必要でした。
そうしたことから、明治二年、兵部省を設け、陸海軍・軍備、兵学校などを管理することになります。
こうした政府の動きは、名古屋城にも多大な影響をもたらすのです。
名古屋鎮台の設置にともない、明治初期の「旧物破却」の風潮もあってか、名古屋城には次々に陸軍の施設が建てられ、景観が一変します。
明治四年に三之丸の武家屋敷が、六年にはとうとうニ之丸御殿なども取り払われてしまいました。
その後も名古屋城は陸軍にとって重要な拠点として、施設の充実が図られます。
また、明治二十四年にはのちの首相桂太郎が、名古屋鎮台から改められた第三師団に赴任して、尾張の若者たちを率いて日清戦争へと突入します。
このように、その所管が宮内省に移されるまで、名古屋城は時代に翻弄され続けました。
[K]離宮三十七年半もの間、名古屋城を名古屋城と呼ばない時期がありました。
明治を迎えるや早々に、城は陸軍省に管理されることになりましたが名称は変わりなく名古屋城でした。ところが明治二十六年、管理が陸軍省から宮内省へ移り、その名も「名古屋離宮」ということになったのです。
離宮とは、皇居のほかに定められた宮殿のことで、ここ「名古屋離宮」は、天皇や皇后を迎えること五十余度、明治四十四年には旧江戸城の蓮池門を移して、離宮正門とされました。
また、先の濃尾大地震(明治二十四年)でこわれた西南隅櫓は、大正十二年に宮内省によって修復されました。そのため、隅櫓の鬼瓦や花瓦には、尾張徳川家の葵の紋ではなく、菊の紋章が付けられ、いまも残されています。
時代は昭和となり、五年十二月、離宮は宮内省から名古屋市へ下賜され、名古屋城の呼び名も復活しました。
名吉屋市は、それまで許されていなかった城の一般公開を翌年二月にさっそく実現したので、開放を喜び、多くの市民が足を運びました。
正門に向かって左手にある「恩賜元離宮名古屋城」の石碑は、こうした歴史を物語るものです。
[L]再建宝物のように大事にしてきた名古屋城が焼け落ちてしまい、いまはもうない。
焼け焦げた石垣だけが残きれた光景は見るにしのびない。
誰もがそんな気持ちだったのでしょう。
名古屋城の再建を願う動きは、戦後まもなくしてみられるようになりました。
声は日増しに高まり、機連が熟しました。
昭和三十年、名古屋市も再建への動きを始め、翌年には名古屋城再建準備委員会が開催される運びになりました。
再建のための地質調査や再建費の捻出の方法も話し合われました。
そして、いよいよです。市民の声に抑されて、再建に向けた事業がスタートしました。
費用集めの幕金には市民はもとより県民や国の内外からも多くが寄せられ再建実現に向けて大きく前進しました。
募金者の氏名は冊子に記録され、名古屋城に保管されています。
昭和三十二年、天守閣再建の起工式が挙行され、二年後の竣工が現実のものとなりました。
ところが、竣工予定の四日前、伊勢湾台風が東海地方を直撃し、市内の被害が甚大だったために、竣工行事は縮小され簡素に行われました。
こうして名古屋城(大・小天守)の再建は叶い、新たな歴史を開いたのです。