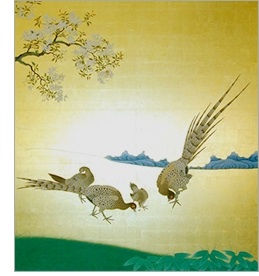2018年度 第4回研修会 大須ガイド研修 2018年 9月 30日
大型で強い勢力の台風24号が夕方から夜にかけてこの地方に接近するという30日の午前中、今年度第4回研修会として 「下町の雰囲気を醸す大須のガイド研修」 が行われました。
参加者は29名、4グループに分かれ AGGN の会員が案内、外国人ゲストはどんな店に興味を示すのか、どんな土産物を買うのか、などを紹介しながら大須商店街を散策しました。
また、昨年できた白龍モニュメントなど一見お寺には見えない派手な万松寺、大須のシンボルでもある朱塗りの大須観音、小さくて目立たないが歴史を感じさせる富士浅間神社の、三つの異なる景観の寺社を楽しみました。
予定していた二つの「からくり」は雨や故障中で見学できなかったのが残念でしたが、参加者の皆さんは大須散策を楽しまれたようで、研修後のアンケートでは「参考になった」、「大須のガイドをしてみたい」との声が聞かれました。
台風接近中でしたが研修中はほとんど傘を差さなくて済み、12時に解散した後、皆さん足早に帰路につかれました。 (藤井 記、写真提供 村松)